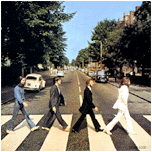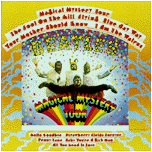
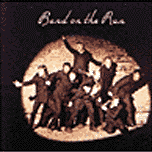
ビートルズ解散後に結成した新バンド「ウイングス」の’73年のヒット曲。ビートルズ解散直後の’70年代前半というのは、今からは信じられない話だが、ポールに対する世間の風当たりが妙に冷たい時代だった。順調にヒットこそ飛ばしているものの、やはりビートルズ脱退宣言からくる「解散の原因=悪者」のイメージが後をひいていたのかもしれない。しかし、そんな風潮もこの曲の大ヒットから徐々に形勢が変わり始める。インパクト充分のイントロに始まり、英語圏以外の人間でもすぐさま口づさめる覚えやすいコーラス、アタックの効いたロック・サウンド等々、鮮やかなまでのポップ・センスに彩られたこの曲は、明らかにポールが新しい章に突入したことを告げていた。つまりこの曲は『バンド・オン・ザ・ラン』~『ヴィーナス&マース』~『スピード・オブ・サウンド』とウルトラ名作連発時代の幕開けを告げるファンファーレのようなナンバーなのである。ポールもきっと印象深いナンバーに違いない。ウイングス時代だけでなく、89年以降の3回のソロ・ツアーでも、必ずこの曲が演奏されていることからもそれはわかる。
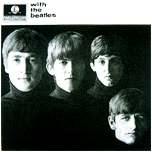
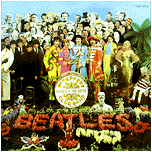
タイトルに端的に表れているように、ポールの陽気さが全面に出たポジティヴ・ソング。ただ、収録された作品が’67年の『サージェント‥』という、ヒット性よりも実験性が重んじられたアルバムだったため、全体の中ではやや「浮いた」印象しか与えていなかったのも確か。しかし、冷静にこの曲単体で聞き直してみれば、ビートルズらしいコーラスや小気味よくシャッフルするギター・リフなど、キャッチーな要素が充分に盛り込まれた秀作であることに気づく。ファンの間では実は密かな人気曲、という話も納得がいくところだが、おそらくそのあたりを突いてきた「ニクい」選曲だろう。ちなみに、この曲がライヴで演奏されることも、今回のツアーが初めて。
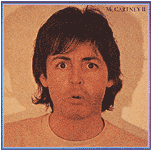
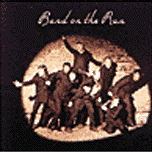
ウイングス時代から、ライヴではおなじみのナンバー。ポールには珍しく、へヴィでタメの効いたロック・ナンバーだ。ポールはこの曲をかなりお気に入りの様子で、ツアーで何度も取り上げているだけでなく、’01年の2枚組ベスト・アルバム『ウイングスパン』では2枚目のディスクの冒頭にこの曲を置いてさえいる。曲としてはシンプルなブルース・ロックをやや現代的にアレンジしたもの、と言っていいと思うが、スローな演奏がじわじわとスリル感を演出してくる、という展開はやはりポールにしては異色の作品。ライヴでのポールはこの曲ではギターに持ち替え、たっぷりと「間」の効かせたメイン・リフを弾いている。


そのアルバムのタイトル曲だが、タイトルが示すとおりにこれまた切なくも激しいナンバーだ。ただしこの曲は、そんなうねりのあるサウンドの中でも、なかなかにキャッチーなメロディやフックが用意されているところがポイントで(歌いだしの~♪ワン・ツー・スリー・フォー・ファ~イヴ~とかね)、ソングライターとしての熟練技を隠し味的に見せ付けてくる。歌い方はワイルドでも、メロディだけを見てみると実はなかなかにスイート。ポールの曲にはこんなことがよくあるのだ。

ロックに年齢は関係ないことを如実に教えてくれるパワー・アルバム『ドライヴィング・レイン』だが、もちろん美しいバラッド・ナンバーもソツ無く用意されている。やはり一般的には“ソフトで心温まる名曲を作る人”というのがポールのイメージだと思うが、最新アルバムにおいてそんなリクエストに応えてくれているのがこの曲。ピアノの弾き語りで始まるポールお得意のナンバーだが、中盤からバンド演奏に突入すると、スロウな曲ながら俄然熱っぽさが増してくるあたりは、やはりこの『ドライヴィング・レイン』というロックン・ロール・アルバムへのポールの特別のこだわりなのだろうか。ライヴではさらに熱っぽい盛り上がりが期待できるドラマティックなナンバーである。
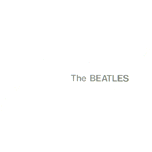
ビートルズが’68年にリリースした2枚組オリジナル作『ザ・ビートルズ(通称ホワイト・アルバム)』に収められていたフォーク風のナンバー。ここでバンドのメンバーはいったんステージを去り、スポット・ライトの中にポール一人が残ることに。生ギターに持ち替えての弾き語りタイムだ。過去のライヴでは、何気なくポロポロとギターをいじるふりをしながら唐突にこの人気曲に突入し、場を「あっ」と言わせる展開が定番だったのだが、そんな(いい意味での)「悪戯心」もまだまだ健在なことだろう。それにしてもこの人はアコースティック・ギターが巧い。微妙なテンションをコードに乗せながら、同時にメイン・メロディまでを重ねてしまう技量には、もはや他人のヘルプなんぞ不要。一人で好き勝手やってもらうのが一番!と誰もが思う瞬間なのではないだろうか。
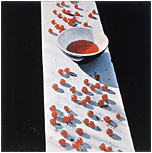
‘70年のファースト・ソロ・アルバムに収められていた小作品。これも、生ギターをいじっていたらいつの間にか出来てしまったような軽い乗りがいい。MTVアンプラグドでも披露されていたが、そんなほのぼのとしたムードにマッチングする曲だ。♪ウ~ウ~ウ~とハミング風のコーラスは誰もが簡単に歌える気軽さもあり、コンサート中盤のリラックス・タイムをうまく温めていくことだろう。
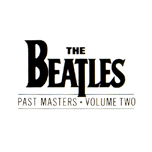
ビートルズ’65年の大ヒット・ナンバー。この曲もビートルズ時代にはライヴのレパートリーに入ったことはなく、’93年のニュー・ワールド・ツアーが初披露だったが、その時に引き続いての登場だ。昨年、新たにCDフォーマットで編集されたベスト・アルバム『Beatles 1』にも当然収録されていたが、そのためかこの曲の新世代への人気が現在改めて高まっているという。ラヴ・ソングを卒業し、ミュージシャンとして成熟した作品内容へと向かいつつあった時期の作品だけに、歌詞の内容も曲調もポップ・ソングでありながら同時にややシリアスでもあり、そんなところが時代を超えた共感を呼び起こすのだろう。
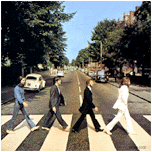
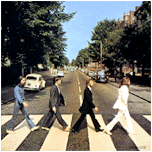
そして、いきなりこの曲につなげていくあたりが、これまた意表をついたところでもある。その「アビイ・ロード・メドレー」の終盤に登場するナンバーで、観客一体となっての大合唱が起こるナンバーだ。あのメドレーをどのようにダイジェストするのか、ポールも相当頭を悩ませたことと思うが、しかしこんな贅沢な悩みも無いといえば無いだろう。結果、やや大胆な編纂にはなったが、しかしあのスケール感はこの2曲だけでも存分に表現されているのではないかと思う。
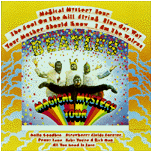
続いて、ピアノ・ナンバーの定番曲のひとつである、この曲。初出は、ビートルズ’67年のTV映画『マジカル・ミステリー・ツアー』のサントラ盤だが、この曲もシングル・カットされていない割には、多くのベスト盤に収められたり、多くのカヴァー・バージョンを生むなど印象の強いナンバーだ。映画でもポールがフランスへの単独ロケを敢行し幻想的なシーンを撮影したが、その映像の味わい深さも大きなポイントになっているのかもしれない。
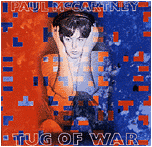
ジョン・レノンが凶弾に倒れたのは、’80年12月のことだった。ショックは世界中を駆け巡り、ポールもしばし活動休止状態に入ってしまう。しかし、その思いを胸に全身全霊を賭けて製作されたアルバム『タッグ・オブ・ウォー』は、曲・演奏ともに最上級の水準を誇る傑作であり、結果的に’80年代のポールを代表する名作となる。多種多様なアイデアや曲調が、ビートルズ時代のプロデューサーであるジョージ・マーティンとの阿吽の呼吸でまとめられたボリューム感たっぷりの内容だったが、その中にあって3分にも満たない地味なこの曲こそが、ストレートにジョンへの追悼の意を表した曲だった。往年の名曲「イエスタデイ」にちなんだアコースティック・ギターのバラードであり、背後にストリングスを配したアレンジを施すなど、往年のビートルズを彷彿とさせるアレンジが、当時多くのリスナーの涙を誘った。
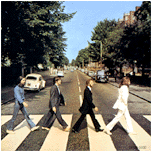
そして’01年は、再びビートルズ・ファンが悲しみにくれる年となってしまった。11月のジョージ・ハリスンの死去については、すでに病状は刻々と伝えられてはいたものの、しかしこんなにも早く“その時”が訪れようとは、誰も思ってはいなかっただろう。ジョージへの追悼の意として、ポールは彼の代表作であるこの曲を今ツアーのメニューに加えることにしたのだ。先に述べたビートルズのラスト・アルバム『アビイ・ロード』は、ビートルズの最高作のひとつというだけでなく、ビートルズ時代のジョージ最大のヒット曲であるこの曲が収められていることでも知られている。晩年、ジョージはウクレレに凝っていたそうだが、ポールは彼から送られたウクレレを弾きながら、この曲を歌うという。
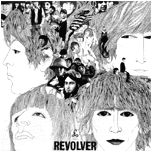
追悼曲2曲に引き続き、情感を込めて切々と歌われるこの歌は、ビートルズ’66年の作品『リボルヴァ-』からの一曲。教会で一人寂しく葬られた少女エリナーをしみじみと歌ったこの曲は、前2曲の荘厳なムードを静かに締めくくる意味でここに置かれたのだろう。オリジナルは弦楽8重奏の荘厳なアレンジが出色の出来だったが、’90年のツアーではややスローにテンポを落としての朴訥なヴォーカル、そして静かなシンセのアレンジが印象に残った。果たして前2曲を受けて歌われる今回のライヴでは、どんな表情がうかがえるのだろうか。
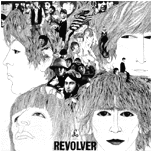
『リボルヴァ-』からの曲を連続してくるところはちょっと意表をつくところ。しかし、ビートルズの作品群の中でもポールはこのアルバムに特別の愛着を持っているようで、'84年の彼の監督・主演映画『ヤァ!ブロード・ストリート』でも、サウンド・トラックにこのアルバムから4曲もピック・アップしていたくらいである。この曲もスロー・バラードだが、前曲と違うのはこちらはちょっとした陽光を感じさせる暖かさが胸に沁みるナンバー。’93年のニュー・ワールド・ツアーでも登場しており、次の場面への橋渡しを告げる予告編にピッタリのナンバーかもしれない。
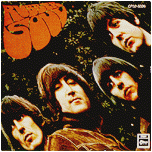
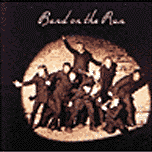
‘73年、ポール&ウイングスにとって起死回生となったアルバムのタイトル曲。もちろん、シングルとしても大ヒット。ポール健在なり!を世界中にアピールした記念すべきナンバーである。なにしろ、1曲の中に詰め込まれたアイデアの量が半端ではない。通常の3曲分くらいの情報量で起承転結を見せるこの曲は、実際いくつかのパートに分かれており、歌のテーマである「脱出→自由」といったストーリーを見事に音とメロディで表現した快作である。それは、それまでのさまざまなしがらみから自らを解き放ち、新しい環境で新しい音楽を創造することを願っていた当時のポールの気持ちそのままだったのかもしれない。だからこそ、彼は必ずライヴでこの曲を演奏するのだ。
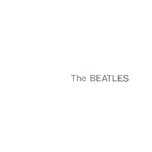
古典的ロック・ナンバーとしてはポールの代表作ともいえるのが、この曲。ビートルズ’68年の自由奔放作『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』の冒頭を飾ったハード・ドライヴィング・ナンバーだが、この歌、実はよく聞いてみると、コーラスといいサーフィン・タッチの曲調といいタイトルといい、チャック・ベリーの「バック・イン・ザ・USA」、ビーチ・ボーイズの「サーフィンUSA」等々、数々のヒット・チューンのパロディで出来ているのだ。そんな遊び心やユーモアが常に根底にあったところも、ビートルズの大成功を考えるときに欠かせない要素ではないかと思う。しかし、それはそれとして、まずはロックンローラー・ポールのパワフルなヴォーカルに耳を傾けたいところだ。
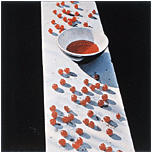
ビートルズ解散のドタバタ劇の中に突然リリースされた初のソロ・アルバム『マッカートニー』は、スコットランドの自宅で彼が(当時としてはかなり珍しかった)一人多重録音で製作したため、シンプルな小作品といったものが数多く収録されていた。そんな中にあって、この曲だけは完全なバンド・アレンジが施された壮大なスケール感を誇り、またバラード・タイプの曲でありながら、金切り声にも似たパワフルなシャウティングでドラマティックな盛り上げを聞かせる、アルバムの最大の山場を飾っていた曲だった。ソロ・アーティストではあっても、やはりバンドマン魂が消えてはいないことを示したこの曲は、71年にウイングスを結成するや当然のようにライヴ・レパートリーに加えられ、その後もほぼ定番ナンバーとなった名曲。ちなみに、’76年にウイングスのライヴ・アルバムからのシングル・カット・バージョンがヒットしたが、その時は「ハートのささやき」という新邦題が付けられている。
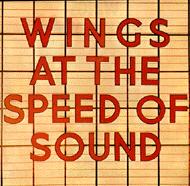

ポールならではの甘美なメロディー・センスが発揮された'73年の大ヒット・ナンバー。ここで歌われている“マイ・ラヴ”とはもちろん、'98年に乳癌で亡くなった往事の妻・リンダのことで、ポールはピアノの前で切々と思いの丈を歌っている。イントロなし、アウトロもなし、という展開は一見珍しいが、実はポールがよく使う技で、あくまで歌メロのアピール力に賭けようとする姿勢がうかがえる部分である。
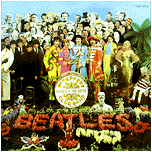
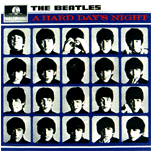
破竹の勢いで人気急上昇だったビートルズが、’64年に初めて主演した映画『ア・ハード・デイズ・ナイト /
ビートルズがやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!』に挿入されていたロックンロール・ナンバー。シングルとしてもリリースされ、当然のようにNo.1ヒットを記録している。これまたイントロなしのシャウトでスタートし、息着く間のないスピード感で走りぬけた後、アウトロもないままに唐突に終了し大いなる余韻に聴く者を包み込むのは、先述したように彼の得意技。映画では、彼らが野原を走り回るシーンで流れたため、事更にめまぐるしい印象の強い曲だが、あの輝くようながむしゃらさ~若さは見ていて本当にまぶしいものだった。名場面の多いあの映画の中で、ここをもっとも好きなシーンにあげる人も少なくない。
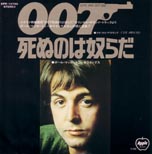
‘73年前半は、ビートルズと比較された時に、今ひとつ足踏み状態が続いているような状態ではあったが、再びジョージ・マーティン・プロデュースの下、
007映画の主題歌を手がけたポールは、目の覚めるような名曲を誕生させる。3分強の短い作品ながら、動 / 静 の対比を上手く取り入れたメリハリに富んだ仕上がりは、
その後のポールのライヴでもアクセントとなるナンバーとして重要なポジショニングを担っていく。後年、ガンズ&ローゼズがカヴァー・バージョンを発表し、この曲に新しい息吹を与えたことはご承知の通り。

ビートルズの、そしてポールの代表曲のひとつ。ビートルズの末期を辿ったドキュメント映画『レット・イット・ビー』の表題曲であり、シングルとしても全世界でヒットしたナンバーである(日本では、彼ら最大のヒット・シングルとなった)。荘厳なピアノのコード、ややシリアスなポールの口調からは
賛美歌にも似た慈悲深さが感じられるが、当時終焉に近づいていったビートルズにあって、実は一番解散を望んでいなかったポールが胸のうちを語ったナンバーとも言われている。ビートルズ・ナンバーを全面的に解禁した’89年以降のライヴでは欠かせないレパートリーとなっている。

そしてポールを語る上で、決して忘れられないのがこの曲。’68年、ついに自身の会社「アップル」を設立したビートルズが、第1弾シングルとしてリリースし、結果的にバンド史上最大のヒットとなった曲である。語りかけるようにはじまるピアノの弾き語りに、徐々に一人一人が演奏に加わっていく展開は、決して派手ではないがバンドの楽しさを充分に感じさせるもので、その揺るやかな高まりが最終バースを歌い終わった後の、あの延々と続く♪ダ~ダ~ダ~、ダダダッダ~(あれは「ナ」といっている、と主張する人もいるが)というコーラスへとつながっていく構成もまたお見事である。これもポールのポップ・センスが冴えまくった、世界中英語圏以外でも、しかも大人から子供まで分け隔てなく歌える歌の好サンプルであり、彼のソング・ライターとしての本領発揮作ともいえるものだと思う。
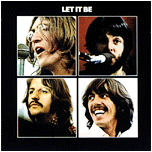
アンコールの1曲目は、これもポールらしいピアノ・バラードで始まる。映画『レット・イット・ビー』で登場し、’70年の同名アルバムにも収録された人気曲だが、ビートルズの解散劇の騒動のさなかにリミックス作業が行われたため、ポールには不本意なバージョンがアルバムに収録されてしまったことは有名である。それでもポールはよほどこの曲自身は好きらしく、’75~6年のワールド・ツアーだけでなく’89年代以降のツアーでも好んで歌っており、しかも面白いことにオリジナルのアレンジに固執するのではなく、時にブラス・セクションを加えたり、時にサックスにソロをゆだねたり、毎回さまざまな新アレンジを施しているところが面白い。果たして、今回はどんなアレンジが聞けるのだろうか。

美しいバラードから一転して、転がるようなファンキーなピアノのリフが始まると、それはビートルズ'68年のヒット曲「レディ・マドンナ」だ。古いタイプのジャズやボードビルにも精通したポールならではの作品で、発売時は妙に太く黒っぽいポールの歌声をリンゴの声と思い込んでいたリスナーも多かったとか。この曲もライヴ映えするナンバーゆえ、ポールのステージでは‘70年代から頻繁に取り上げられている曲である。
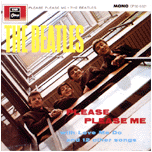
そして登場するのは、ビートルズ’63年のファースト・アルバムから、しかも冒頭を飾っていたこの曲。若き日のビートルズが憧れたリトル・リチャード直系のドライヴィング・ロックン・ロールである。バラードの名手として知られるポールだが、でもスタート地点は熱いロックなんだぜ!といわんばかりの熱唱を聞かせる場面だ。そして、最も古いレパートリーというだけではなく、ポールにとって特に思い出深いのは、80年代後半、英国で皇室を讃える「プリンス・トラスト・コンサート」に多くのミュージシャンに混じってポールが出演した時のことだ。大ラスの全員参加の場面でこの曲が取り上げられ、リード・ヴォーカルを取るポールは背後から多くのミュージシャンたちの暖かい眼差し、そして敬意を肌で感じたという。その感動から自分自身も長く休んでいたツアーに再び出ることを決意した経緯もあり、言わば二つの意味で、ポールのキャリアの重要な契機となったナンバーなのだ。そんな思い入れも感じながら、しかし飄々としたロックンロールでかっ飛ばすポールのシャウティング・ヴォーカルに、ここはひとつ一緒になって叫びたい。
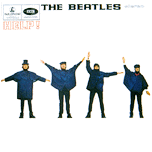
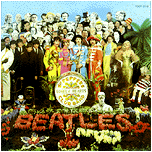
ビートルズの実験精神が最大風速を記録したことで知られる’67年のアルバムのタイトル曲。アレンジやスタジオ・テクニックに凝りまくったアルバムというだけでなく、それらの楽曲を「サージェント‥」という架空のバンドが演奏している、という設定を冒頭のこの曲で宣言し、アルバム全体に一本の統一テーマを設定したことから「コンセプト・アルバム」の走りとも言われている。まず司会者の観衆への挨拶から始まり、バンドを紹介するところから順番に進行していく様子をそのまま歌にしてしまったアイデアも卓越だが、それ以前にひとつのポップ・ソングとして充分に魅力的なものになっているところが素晴しい。アルバムでは、この曲から切れ目無く2曲目以降へと続いていくわけだが、今回のライヴでは少しく意外なところへ飛び火していく‥。